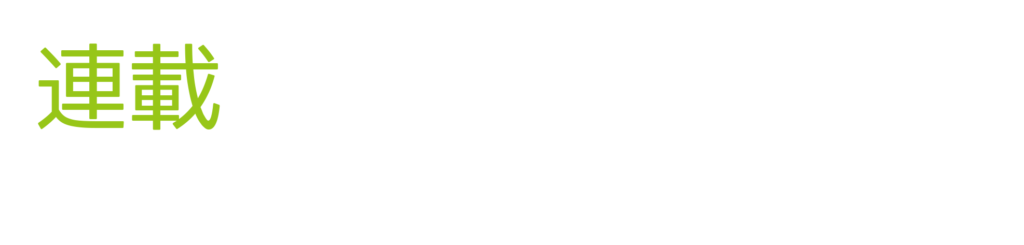在宅介護歴23年。
自由奔放に生きる娘に
何が起きたのか。
自由奔放に生きる娘に
何が起きたのか。
<新連載>eps.1 エロイーズ
- 椋平州魅子 ムクヒラスミコ : 2019年より当法人の広報担当 2021年より組織デザイン、人材教育担当

1985年、私は急な坂道の上に建つアパートメントに住んでいた。窓から見下ろすとケーブルカーが音をたて、ノロノロと走っている。ヴィクトリアン調の小さなアパートメントには8人が住んでいて、そのほとんどがシングルだ。

エロイーズは私と同じフロアに住む高齢の女性だ。若くして夫に先立たれた後入居し、ポストオフィスをリタイヤした後もずっと住み続けている最長の住人だ。象のような足でかなり太っていて、外出時はきちんとした服装で必ずカツラをかぶっている。階段の途中で立ち止まっているのを見かけると、ショッピングカートを持ってあげたりした。部屋まで運ぶと言っても、彼女はいつも断る。
ある日私の電話が通じなくなり、エロイーズに電話を借りたことがある。その時も部屋には入れてくれず、電話機をドアの外まで持ってきた。その理由は後にわかった。
夜帰宅すると、住人兼管理人のトリスが激しくドアを叩いた。エロイーズが心臓発作を起こし、救急で入院したと言う。裸でベッドに寝かされていたことに同情したトリスは、彼女の部屋着を持って行くのだと話してくれた。

幾日か過ぎ、今度は相談したいことがあると言われた。エロイーズの部屋が驚異的な状況で、退院後まともに暮らせる環境ではないと。部屋をきれいにして迎えてあげたいと前置きし、トリスは私に片付けを手伝って欲しいと言った。
はたしてエロイーズの部屋は、ベッドからバスルーム、キッチンルームへの動線があり、その幅50cm程はすり足の汚れで出来ていた。動線の両脇は新聞や芸能雑誌、食品トレーやタバコの空き箱などが、びっしりと腰の高さまで積み上がっていた。ベッドは片側だけが大きくくぼみ、壁には新しいマットレスが立てかけられ、数十個のギフトは開けることなくクロゼットに突っ込まれていた。
エロイーズの部屋は50’sスタイルで、入居以来一度もリノベートされていなかった。調度品はどれもアートデコの上品なものばかり。ゴミをすべて出し窓を拭き終わると、部屋のすみずみが明るくなり、ライトを消して作業ができるようになった。

1ヶ月間片づけとゴミ出しをしている間に、エロイーズは帰らぬ人となった。この強烈な経験は、状況を説明できても感じた事は表現しきれなかった。自由に老いることの現実を見せつけられたのだろうか。やがてそれは、後の人生を大きく変えるインパクトを残していた。